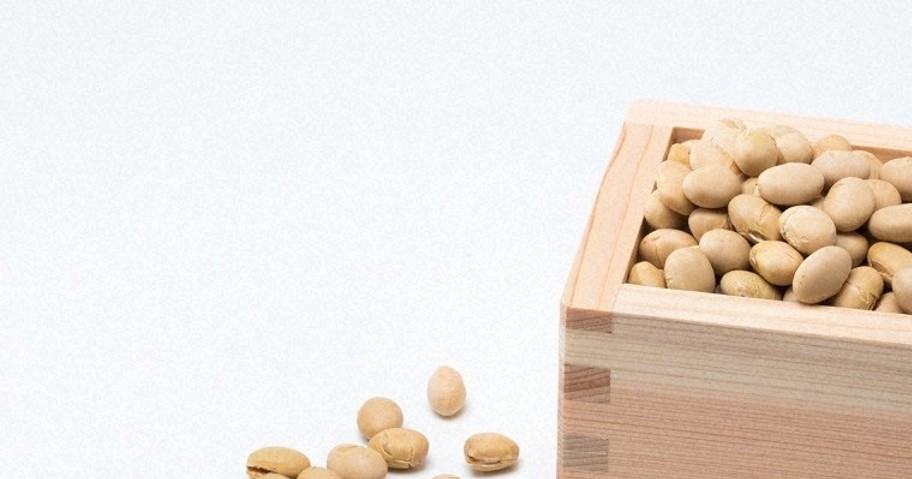福豆(写真はイメージ)=ゲッティ
2日は節分。「節分は2月3日」というイメージを持っている人も少なくないだろうが、実は常に同じ日付というわけではない。しばらく「2月3日」が続いていたが、2021年は1897(明治30)年以来124年ぶりに「2月2日」に。今年は21年以来4年ぶりだ。
節分は「季節を分ける」節目を指す。国立天文台暦計算室によると、かつては「二十四節気」のうち立春、立夏、立秋、立冬それぞれの前日を指していたが、現在は立春の前日だけが残っているという。
Advertisement
二十四節気は、太陽の周りを公転する地球の軌道を24等分して、それぞれの位置にある日を季節を示す目印と決めたものだ。人間が「ここが立春」と決めた位置に地球がある日を「立春の日」とし、その前日である節分の日付も、同じように地球の位置で決まる。日本では、国立天文台が二十四節気が何月何日になるかを計算し、毎年2月に「暦要項」として翌年分を官報で公表している。

地球の位置と日付・時刻がずれるのは?
我々が使っている日付・時刻は、地球が太陽の周りを一周する時間を「1年」とし、うるう年を除き、1年の日数を365日と決めている。だが実は、一周するのにかかる日数はぴったり365日ではなく、365・2422日と1年より少し長い。
つまり、人間が決めた1年という時間では地球は太陽の周りを回りきれず、1年たって同じ日付・時刻になったとしても、軌道上で1年前と同じ位置に到着していないのだ。さらに0・2422日(5・81時間=約6時間)かかってようやく同じ位置にたどり着く。
例えば、ある年の「2月3日午前0時」に、立春の1日前の「節分」に相当する位置に地球があった場合、翌年に地球が同じ位置に来る時刻は「2月3日午前6時少し前」となる。地球の位置を基準にして考えると、日付・時刻の方が1年で約6時間進んでしまうのだ。4年たつと「約6時間×4年分=約24時間(約1日)」もずれる。このままだと、実際の地球の動きと日付・時刻がどんどん離れていってしまう。
このため、日付・時刻を調整してこのずれを補正する。補正の代表例がうるう年だ。4年に1度、1日(24時間)増やして1年を366日にして、地球の動きに対して進んでしまった日付・時刻を調整する。しかし、1年あたりのずれは6時間よりやや短いため、4年分のずれの合計は24時間に達していない。そのため、うるう年で一気に24時間を補正すると、今度は逆に日付・時刻の方が約45分遅れてしまうことになる。
この約45分の日付・時刻の遅れは、うるう年のたびにたまっていき、400年たつと約3日分にまで増える。それに対応するために、うるう年を400年間に3回減らして、日付・時刻の遅れを解消する。本来はうるう年になる順番だった年のうち、「400年に3回減らす」ルールに基づいてうるう年にしなかったのは、直近では1900年で、次は2100年の予定だ。
こういった日付・時刻のずれや補正によって、節分の日付が変わってしまうことがある。21年や今年の節分が2月2日になる理由だ。
過去を見ると、「400年に3回」の補正をした1900年以降84年までの間は、節分の日付は2月3日か4日だった。その後、85~20年の間は、毎年のずれや日付・時刻の調整があっても節分は毎年2月3日に収まっていた。そして20年のうるう年の調整によって、翌年の21年に節分は2月3日の24時間以内に収まらなくなり、2月2日になったというわけだ。
ただし、地球の動きに対して日付・時刻は毎年約6時間進むので、22年の節分はまた2月3日になった。21年の次に節分が2月2日になったのが、うるう年の翌年である今年。このようにしばらくは4年に1回、うるう年の翌年の節分が2月2日になる。2058年から90年までは、うるう年の翌年と翌々年、つまり4年に2回は節分が2月2日になる。【柳楽未来】